
【最新手口】自動音声ガイダンス詐欺が急増!巧妙な手口と被害防止策を解説
自動音声ガイダンス詐欺の概要
自動音声ガイダンス詐欺とは、詐欺グループが自動音声を利用して被害者に連絡を取り、指示に従わせて金銭を騙し取る手口です。従来の詐欺手法と比較して、犯人が直接話すことなく多くの人に同時にアプローチできるため、効率的に詐欺を行うことが可能となっています。また、公的機関や大手企業を装うことで、被害者の警戒心を和らげる狙いがあります。
最近の事例
事例1:NTTを騙る詐欺
2024年12月、愛媛県松山市の70代女性が、自動音声でNTTを名乗る電話を受け、「未納料金が発生しているため法的手続きに移行する」との案内を受けました。指示に従って操作を進めると、総務省の職員を名乗る男性につながり、「犯罪の被疑者である」と告げられました。その後、「疑いを晴らすためには現金を送る必要がある」と指示され、女性は指定された住所に現金1000万円を送付し、騙し取られました。
事例2:携帯電話会社を装った詐欺
2023年5月、岐阜県各務原市の30代女性が、自動音声で「ご使用の携帯電話は明日以降使用できなくなる」との連絡を受けました。案内に従って操作すると、携帯電話会社の社員を名乗る男性につながり、「個人情報が流出している。このまま警察署につなぐ」と言われました。その後、警察官を名乗る男性から「口座を調べる必要がある」として、指定の口座に計13回、合計約635万円を振り込むよう指示され、被害に遭いました
事例3:電話料金未払いを装った詐欺
2024年2月、東京都目黒区の50代女性の自宅に「電話代の未払いがあり、利用を停止する」との自動音声の電話がかかってきました。音声に従って操作すると、電気通信事業者の社員を名乗る男性につながり、銀行の口座番号などを教えるよう求められました。女性は口座番号を伝えましたが、近くにいた親族が不審に思い、詐欺と気づき被害を免れました。
自動音声ガイダンス詐欺の手口
自動音声ガイダンス詐欺の一般的な手口は以下のとおりです
- 自動音声での連絡:被害者の電話に自動音声で連絡し、「未納料金がある」「個人情報が流出している」などと伝える。
- 操作の指示:音声案内に従って特定のボタンを押すよう指示し、被害者を詐欺グループのメンバーにつなげる。
- 信頼させる:公的機関や大手企業の職員を名乗り、被害者に信頼感を与える。
- 金銭の要求:「疑いを晴らすため」「口座を確認するため」などの名目で、現金の送付や振り込みを指示する。
被害を防ぐための対策
自動音声ガイダンス詐欺から身を守るためには、以下の点に注意することが重要です:
- 自動音声の指示に従わない:不審な自動音声の電話がかかってきた場合、指示に従わず、すぐに電話を切る。
- 個人情報を伝えない:電話で口座番号や住所などの個人情報を求められても、安易に伝えない。
- 公式窓口に確認する:不審な連絡があった場合は、必ず公式の窓口(企業のカスタマーサポートや自治体の問い合わせ窓口など)に連絡し、事実確認を行う。
- 録音機能を活用する:スマートフォンの通話録音機能や、固定電話の迷惑電話防止機能を活用し、証拠を残す。
- 周囲に相談する:詐欺被害に遭う前に家族や警察に相談し、一人で判断しないようにする。
- 詐欺対策アプリを利用する:迷惑電話フィルターアプリや、着信拒否設定を活用し、不審な番号からの連絡を遮断する。
まとめ
近年急増している自動音声ガイダンスを利用した詐欺は、公的機関や大手企業を装い、被害者を巧みに誘導して金銭を騙し取る巧妙な手口です。詐欺グループは、電話での直接対話を避け、自動音声を利用することで、警戒心を薄れさせ、より多くの人をターゲットにできるようになっています。
被害を防ぐためには、自動音声の指示に従わないことが最も重要です。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに電話を切り、公式窓口に確認しましょう。また、家族や知人と情報を共有し、周囲にも注意を促すことが大切です。
少しでも違和感を覚えたら、警察(#9110)や消費者ホットライン(188) へ相談しましょう。詐欺被害を未然に防ぐために、正しい知識と対策を身につけておきましょう。






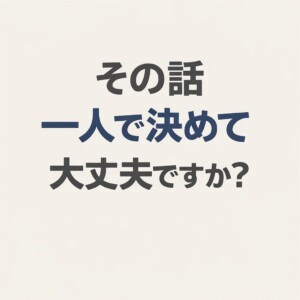


この記事へのコメントはありません。