
「自分は騙されない」思い込みが招く詐欺被害
🧠「私は騙されない」が最大の落とし穴!?
60代以上がSNSフェイク情報にハマりやすい本当の理由とは
📌 SNSフェイク情報の信頼度、半数近くが「まだ信じている」
2025年5月13日に公表された総務省の調査によると、過去に流通したSNS上の偽・誤情報について、約半数(47.7%)の人が「今でも正しいと思っている」と回答。これは非常に驚くべき数字です。
しかし、さらに驚くべきは――特に60代以上に「自分が騙されるはずがない」と思い込む傾向が強く見られる点です。
🧓 なぜ60代以上は騙されやすいのか?
💬 「自分の考えと一致していたから信じた」
60代以上の回答者には、
-
「自分で論理的に考えた結果」
-
「自分の信念と一致していたから」
という**“自信過剰”な理由で偽情報を信じてしまう傾向**が目立ちました。
📺テレビや新聞といった「正統なメディア」をよく見る世代にもかかわらず、自らの先入観を正しいと確信し、誤情報でも疑わない――これは情報社会における新たなリスクです。
🔄 「だまされた」と気づきにくい環境要因も
🚶♂️ 人と会う機会の減少が“妄想”を助長
高齢層は退職や仕事の引退により、日常的に人と会う機会が減ります。すると、
「それ間違ってるよ」と指摘されるチャンスが減る
→ 閉じた世界で誤情報にさらされる
→ 妄想が膨らむ
という負のスパイラルに陥りやすくなるのです。
🎯 実例:「うちの母も陰謀論に…」
NHKの「フェイク・バスターズ」では、
-
「60代の母が陰謀論にハマってしまった」
-
「夫が“ディープステート”を本気で信じている」
といったリアルな声が紹介され、視聴者からも
「うちの家族も同じです…」
という共感の声が相次いだとのこと。
✅ フェイク情報から身を守るためのヒント
1. 複数の情報源を確認する
同じニュースでも、メディアによって表現や見解が異なります。複数のソースを比較することで、情報の真偽が判断しやすくなります。
2. むやみに拡散しない
情報の正確性が不明なまま拡散すると、自分の行動を正当化しようとする心理が働き、間違いを認めにくくなってしまいます。
🔚「私はだまされない」が、最も危険
調査では、35.2%の人が「自分はICTリテラシーが高い」と回答。しかし、これこそが最大の落とし穴。
「私はだまされない」
→ 思い込みが強くなる
→ 偽情報を信じ込むリスクが上がる
この悪循環に陥らないためにも、常に疑い、検証する姿勢が必要です。
📖 出所:YAHOO!<J-CASTニュース>


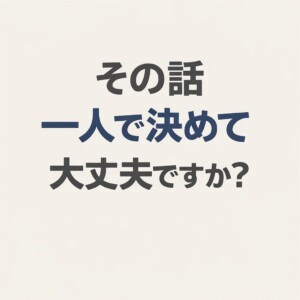






この記事へのコメントはありません。